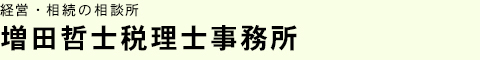建物及び付属設備等の評価
建物及び付属設備等については、土地や株式の評価のような複雑なものではありません。
従って、皆さんも例年5月ごろに市役所や町役場から送られてくる固定資産税の通知書があれば、建物は簡単に評価することが出来ます。
このような簡単な評価方法だけを説明してもつまらないので、相続評価の基となる地方自治体によって算定されている固定資産税評価についても触れてみたいと思います。
これにより、何故現金や預金で財産を所有しているよりも、建物を建築したほうが節税になるのかといった点も納得していただければ、幸いです。
建物のことを、税法では家屋と言っていますが、評価対象となる家屋を自分達で使用しているのか、貸屋なのかによって、評価方法が異なってきます。
①自用家屋
自用家屋とは、貸し付けて不動産所得を得るために有していない家屋のことを言います。
つまり、貸家でない家屋が自用家屋となりますから、次の②貸家の定義から外れていれば自用家屋です。
評価計算方法 固定資産税評価額 × 1.0
つまり、固定資産税評価額そのものが相続税評価額となります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市役所等に「固定資産評価証明書」を発行してもらうことで分かりますが、手数料がかかってしまいます。そこで、例年5月ごろに送られてくる固定資産税通知書を見れば、確認できます。
菊川市の固定資産税通知書を例にとると、次のような表記となっています。
| 所在地番 | 課税地目又は 用途・構造 | 階層 | 評価額(円) | 税相当額 (円) | 固定資産税 | 軽減税額 (円) | 固定資産税 | |||
| 建築年 | 当該年度 課税標準額(円) | 固定資産税 | 前年度 課税標準額(円) | 固定資産税 | 都市計画税 | 都市計画税 | ||||
| 家屋番号 | 課税地域又は床面積(㎡) | 都市計画税 | 都市計画税 | 備考 | ||||||
| 堀之内 ***-* | 居宅 | 2/0 | 15,000,000 | 210,000 | ||||||
| 鉄骨 | H18.8 | 15,000,000 | 45,000 | |||||||
| ***-* | 150.00 | 15,000,000 | ||||||||
上の表の中で、赤く表示したのが、固定資産税評価額です。
つまり、評価額という列の一番上の金額が、相続税評価額となります。
②貸家
貸家の定義は明らかにされていませんが、居宅・店舗等を貸し付けて不動産所得を得るための家屋が貸家であると考えて差し支えないでしょう。
このような貸家の場合の計算式は次のとおりです。
固定資産税評価額 × ( 1 − 借家権割合 × 賃貸割合 )
ここで、借家権割合という言葉と賃貸割合という言葉が出てきましたので、説明を加えますと、
借家権とは、家屋を借りている人が立ち退き要求をされた場合に家主に請求できる権利金のことを意味しています。つまり、家を貸している以上、借主から請求される可能性のある借家権利金相当額を控除して評価しようというものなのです。
借家権割合は、各国税局管内で定められており、静岡県の属する名古屋国税局管内の借家権割合は30%となっています。
賃貸割合とは、例えば1棟で6世帯が入居できるアパートを所有していて、相続開始前から5世帯のみが入居しており、相続開始後も残り1世帯の入居が決まらないような状態の場合には、賃貸割合を5/6として計算するというものです。
③建築中の家屋
上記2つは既に建築されており、固定資産税通知書が届いている場合の評価方法ですが、建築中や固定資産評価をしてもらう前に、施主である被相続人が亡くなってしまうこともあります。
その場合には、建築価格と固定資産評価額の差額を考慮に入れて計算することになります。
このページの最後の方で、固定資産評価のカラクリを説明しますが、多くの場合、建築価格の7割相当額が固定資産評価額となっています。
そこで、課税時期つまり相続開始時点までに建築会社に投下された(支払った)費用原価の額を建築請負契約書や領収証等により確認をして、投下費用原価の70%相当額が建物評価となります。
家屋に付随する付属設備(門、塀、庭木、庭石、あずまや、庭池等)の評価については、面倒な作業が一つあります。それが、再建築価額や調達価額といった金額を算定することですが、知り合いの建築会社や造園事業者に確認すれば、概ねの金額が把握できるはずです。
①家屋と一体となっている設備
家屋と構造上一体となっている電気設備やガス設備、衛生設備、給排水設備等は、会社の経理では建物付属設備として建物とは別の耐用年数で減価償却するのが一般的です。
しかし、これらは建物と構造上一体になっているので、市町村の固定資産税では建物として課税していますので、これらを評価すると重複して評価してしまうことになるため、評価はしません。
評価しないというよりも、建物の価額に含めて評価します。
②門、塀等の設備
門や塀等の外構工事については、次のとおり評価します。
( 再建築価額 − 建築時から課税時期までの期間減価償却額 ) × 70%
ここで、再建築価額と減価償却費という言葉が出てきましたので、説明します。
再建築価額とは、課税時期においてその財産を新たに建築又は設備するために必要な費用額のことをいいます。
建築時から課税時期までの期間に応じる償却費は、定率法という減価償却方法によって計算したものであり、耐用年数は
③庭園設備
④構築物
お問合せ・ご相談はこちら
ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご相談ください
- 結局のところ、費用はいくらかかるの?
- 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
- 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
- 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
- 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?
といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0537-35-2772
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能
お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。
お問合せ受付中
事務所概要
主な業務エリア

静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市
静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市